Twitterを眺めていたら、HP20bというキーワードがでてきました。
なにやらARMを載せていて、gccとかでプログラミングできる電卓とか。
さっそく、HPのサイトに行くと、Developer kit for HP 20b financial calculatorなるものがあり、ZIP形式で開発キットが公開されていました。
サンプルプログラムや回路図やオリジナルのROMイメージなどが入っていて、これはなかなか楽しそうです。
しかも、お手頃の値段になっているとか。HPの電卓にも興味がありますし、昔PC-1500みたいなポケコンとかFX-602Pとかのプログラム電卓も触っていたので懐かしいです。
年内には到着する模様です。これでまたおもちゃが増えてしまいました。
HP20bがおもしろそう
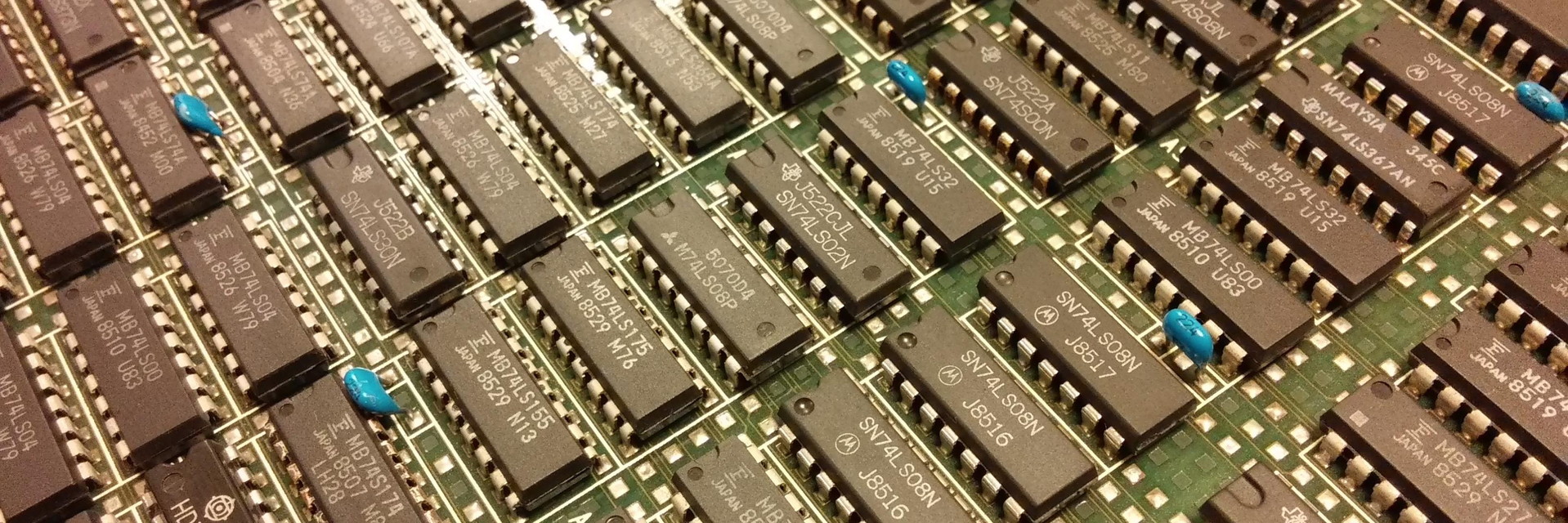 Electronics
Electronics

コメント